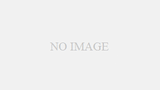はじめに|転職がうまくいかず疲れたと感じているあなたへ
転職活動をしている中で、以下のような悩みを感じたことはないだろうか。
- なかなか面接が通過しない。
- 初めての転職活動で進め方がわからずモヤモヤしている。
- そもそも転職すべきかすら、確信が持てない。
転職がうまくいかない理由は、「能力」ではないかもしれない
日々、企業担当として求人企業と向き合う中で強く感じていることがある。
それは、世の中に“完璧に条件に合致する優秀な候補者”は、実のところほとんど存在しないということである。
特に、自社に対して一定の誇りや実績を持ち、「良い人材を採用しなければならない」と考えている企業ほど、その基準は自然と高くなりやすい。
結果として、「もっと良い人がいるのではないか」と判断が慎重になりすぎ、なかなか採用が進まないというケースは多々ある。
一方で、この構造を生み出しているのは企業側だけの問題ではない。
転職希望者側にも“転職”について考える機会や情報に触れる機会が圧倒的に少ない、という背景があるように感じる。
だからこそ、日頃から「自分をどう魅せるか」に長けている人は、それだけで“優秀そう”に見え、実際に転職活動が順調に進む。
反対に、本来は優れたスキルや経験を持ちながらも、「どう伝えるか」に悩み、結果として転職活動がうまくいかず挫折してしまう人も多い。
かく言う私も、かつては後者であった。あるいは、今でもその感覚を忘れてはならないと自戒している。
現在は、大手人材紹介会社にてリクルーティングアドバイザーとして、法人企業様の採用成功に向けたコンサルティング型営業に従事しているが、最初の転職活動はまさに暗中模索であった。
希望している企業への書類は通らず、やっと掴んだ面接も落ちてしまう。
何よりも苦労したのは、「自分が何をしたいのかがわからなかった」という点である。
情報の集め方が分からず、どの程度まで調べればよいのか、何をどう読み解けばよいのかの感覚もなかった。
結果、自分の経験やスキルをどう整理し、なぜ自分がそれを“できる”と胸を張って語れるのかが、自分自身でも理解できていなかったのである。
だからこそ今回私は、あの頃の自分に伝えたいという思いも込めて、
そして今まさに同じように転職活動を行い悩み苦しんでいる方、あるいは転職活動をしているわけではないが日々の仕事にモヤモヤを感じている方に向けて、
“今からやっておくべき転職の進め方”を、できるだけ具体的にお伝えしていきたいと思う。
ステップ0|転職活動がうまく行かないのは「運」である
まず最初に伝えておきたいのは、転職は運の要素を多分に含んでいるという点である。
転職活動とは、本質的には「その時点で企業側に存在するニーズ」によって成立しているものである。
つまり、企業が“今”必要としている人材を採用するという構造である以上、どれほど能力や経験がマッチしていようとも、「タイミングが合わない」という理由で見送りになることも珍しくない。
実際、転職希望者の中には、「今日の面接で不採用だったから、この企業とはもう縁がないのではないか」と落ち込む方も少なくない。
しかし、それは早計である。今日面接で落ちた企業が、数年後にはまったく異なる条件で求人を出すことは、ごく自然に起こり得る。
もう少し具体的に言えば、(実際に私のクライアントでたまに聞く話だが)
たとえばある企業が「今年は未経験者を大量採用したい。とにかく人手が足りないからだ」と話していたとして、
2年後には「若手が増えすぎたため、今後はリーダー・マネージャークラスの即戦力しか採用しない」という方針に変わっている、ということが実際によくある。
このように、かつて通過していたであろう人が落ち、逆にかつては通らなかった人が求められるようになるという事例は、日常的に見聞きしている。
要するに、転職は努力だけでコントロールしきれるものではないということだ。
「なぜ書類が通らないのか・面接で落ちたのか」ではなく、「今回はご縁がなかっただけかもしれない」と捉えることが、次の前向きな一歩につながる。
転職には運の影響がある。このことは、ぜひ心に留めておいていただきたい。
ステップ1|自己分析:転職の方向性を決める“出発点”
転職活動において最も重要なステップの一つが、「自己分析」である。
これは、今後の転職活動の方向性を定める出発点であり、ここが不明確なままでは、軸のないまま求人を選ぶことになり、結果的に転職後のミスマッチにつながる可能性が高い。
理想的には、「中長期的なキャリアビジョンが明確になっている」状態が望ましい。
しかしながら、実際のところ、そのような状態にある人はごくわずかであるため、現時点で明確な将来像が描けていないとしても全く問題はない。
では、どのように自己分析を進めればよいか。
まずは、一般的に語られる「6つの志向性(※)」の中から、自分にとって今、何が“譲れない価値観”なのかを1〜2つ選び出すことから始めるとよい。
ここで言う「譲れない」とは、どれほど忙しくても、どれほど苦しくても、自分の中で犠牲にしたくないと感じる価値観のことである。
この作業は抽象的に見えるが、実際には日々の生活や将来への思いを具体的に想像していくことで、次第にその核となるものが見えてくる。
たとえば以下のようなイメージである。
【GOOD例】
「将来、家族ができたときに、自分も家族も我慢を強いられる生活にはしたくない」
→ だからこそ、今のうちに社会から求められる存在となり、将来の選択肢を広げておきたい
→ このような価値観は“成長志向”に該当する。
【BUT例(注意が必要な例)】
「今の仕事は残業が多すぎる。だから残業がない職場に行きたい」
→ この思考も決して間違っているわけではないが、あくまで“今の不満”を解消したいという短期的な視点に留まりやすく、根本的なキャリア軸とは異なる可能性がある。
もちろん、現時点での価値観がこの先変化していくことも十分にあり得る。
だが、それでも「今の自分が大事にしたいこと」を言語化しておくことには大きな意味がある。
まずは、焦らず、正解を求めすぎず、自分自身と向き合う時間を設けるところから始めてみてほしい。
※志向性の例としては、成長志向・安定志向・人間関係志向・収入志向・WLB(ワークライフバランス)志向・社会貢献志向などが挙げられる。
ステップ2|求人戦略:自分の転職活動の軸に基づいた選択をする
自己分析によって、自身が叶えたいことや大切にしたい価値観が明確になったら、次はそれを実現できる業界・職種を選定する段階に入る。
(※本稿では割愛しているが、実際はここでさらに深い自己分析を重ねていくことが望ましい)
この求人選定の工程は、転職の成功確率を大きく左右する極めて重要なフェーズである。方向性が曖昧なまま求人を選ぶと、書類が通らない・面接で落ちてしまう等の可能性が高くなり、転職活動全体が長引いてしまう可能性がある。
このタイミングで、ようやくエージェントの力を借りることになる。
ただし、注意しておきたいのは、エージェントにすべてを委ねないことである。
「〇〇業界に行きたい」と単に希望を伝えるのではなく、
「△△という経験が得られる業界・職種を提案してほしい」と伝えるほうが、エージェント側も具体的な意図を汲み取りやすく、マッチ度の高い求人を紹介しやすくなる。
すなわち、方向性を決めるのは自分であり、エージェントはその道筋に必要な情報を補ってくれる存在として捉えるべきである。
少し話はそれるが、私の経験上、キャリアアドバイザーには“ドライバータイプ”(進行や決断を重視するタイプ)が多い傾向にある。
これは決して否定的な意味ではなく、むしろエージェントとして必要な資質とも言えるが、その性質ゆえに、転職希望者側が自分の意志を持たないと、流されるままに話が進み、「何となく進めてしまった」という事態にもなりかねない。
だからこそ、「決めるのは常に自分」であるという意識を持ちたい。
方向性を定めたら、提案された求人群の中から「親和性の高い業界・職種」を選ぶことを推奨する。
理由は単純で、選考通過の可能性が高まるからである。
なお、例外として「大量採用枠」のように条件が広い求人については、必ずしも親和性にこだわる必要はない。
親和性の考え方は主に以下の3つに分類できる:
・商材親和性:これまで扱ってきた商材と近い性質のもの(例:医療機器営業 ⇨ 医療SaaS)
・顧客親和性:これまで向き合ってきた顧客層が同じ(例:法人向け営業 ⇨ BtoBマーケティング)
・顧客側経験:自社で利用者側の立場だった経験がある(例:自社でSFAを導入・運用 ⇨ SFA提供企業)
これらのいずれかに該当すれば、企業側から「欲しい人材」に近いと評価される可能性が高い。
つまり、企業にとっての“コアターゲット層”に入りやすくなるということである。
ステップ3|書類準備:職務経歴書は“伝える設計図”である
職務経歴書の作成は、単なる経歴の羅列ではない。
むしろ、面接で何をどう語るかを設計するための重要な準備工程であり、ここでの完成度がその後の面接での結果を大きく左右する。
実際、この書類作成の段階で多くの失敗が起こっている。
特によく見られるのは、「自分の得意なこと」をそのまま自己PRとして書いてしまうケースである。
もちろん、それが応募先企業が求める能力と合致していれば問題はない。
しかしながら、往々にして「企業が本当に必要としている要素」を無視してしまい、結果としてミスマッチとなる例が少なくない。
実例を挙げると、私自身も初めて転職活動をした際、まさにこの失敗を経験している。
当時、私はメーカーで法人営業を担当しており、顧客課題のヒアリング力には一定の自信があった。
そのため、コンサルティングファームの面接でもその点を前面に押し出した自己PRを展開したのだが、結果は不採用。
今振り返れば、コンサルタント職においては論理的思考力や課題解決力、ドキュメンテーション力などが重視されるポジションであり、見当違いのアピールをしていたことになる。
このように、自己PRとは“自分が話したいこと”ではなく、
「応募先の企業がどのような人材を求めているか」を理解したうえで、そのニーズに合わせて構築すべきものである。
とはいえ、企業が求めている人物像を正確に読み解くことは決して簡単ではない。
求人票だけでは読み取れないことも多いため、この段階ではエージェントの力を借りることを強く勧める。
エージェントは企業と直接コミュニケーションを取っており、「書いてあることの裏にある採用意図」まで把握していることがある。
その視点を取り入れることで、より企業の期待に即した“伝わる職務経歴書”を作成することができるはずである。
※以下リンクのような特化型のエージェントであれば、より密度高くあなたに寄り添ってフォローをしてくれるだろう。
ステップ4|面接準備:相手に合わせて“伝え方”を調整する
転職活動において、面接対策は決して軽視してはならない工程である。
特に「臨機応変な受け答えに自信がない」という方にとっては、事前の準備が結果に直結すると言っても過言ではない。
最も効果的な準備方法は、企業と直接やり取りをしているエージェントに事前情報を聞くことである。
中でも、両手型(RA・CA両方を担当している)エージェントや、企業の担当者として関わっているRA(リクルーティングアドバイザー)に確認するのが望ましい。
この理由は単純である。
企業ごとに面接官の属性や評価ポイントが異なるため、面接ごとに「誰が出てくるのか」「何を見ているのか」を理解しておくことが必要不可欠だからである。
たとえば、よくある面接構成の一例としては以下のような形が多い。
- 1次面接:人事担当者が実施。主に志望動機や人柄、カルチャーフィットなどソフト面を重視
- 2次面接以降:現場責任者が登場。実務スキルやテクニカルな観点を重視
このように、面接官の立場や目的に応じて、見られているポイントが変わるため、質問の傾向や答え方も調整する必要がある。
なお、事前にエージェントから受け取った情報が「当たり障りのないものばかり」であった場合、以下の2つの可能性を考えるべきである。
- 求人自体のハードルが低い
例:販売・接客職や大量採用枠など、特段の準備を求められないケース - エージェントの情報力が不足している
例:大手人気企業や1名限定枠の求人などで、十分な情報提供ができていないケース
後者の場合は、エージェントから得られる情報に過度に依存せず、自ら求人内容を読み解く力が必要となる。
(この「求人の読み解き方」については、別の機会に改めてまとめたいと考えている)
おわりに|「転職の進め方」に正解はない。うまく行かないことが多いからこそ、自分なりの“納得解”を積み上げていく
以上が、私がかつての自分に、そして今まさに転職活動に悩む方や疲れてしまった方に伝えたい「転職を成功に導くための5つのステップ」である。
転職は情報戦であり、感情戦でもある。
目に見える経験やスキルだけでなく、それをどう伝え、どう選択し、どう決断していくかという一連のプロセスそのものが、結果に大きく影響を及ぼす。
どれか一つのステップを疎かにすれば、たとえどれほど優れた能力を持っていても、うまく伝わらずに埋もれてしまうこともある。
逆に、一つひとつのステップを丁寧に積み重ねていくことで、自分にとって「納得できる転職」が近づいてくる。
そして何より伝えたいのは、「正解の転職」は存在しないということである。
転職とは、過去の延長ではなく、これからの自分の“軸”をどう築いていくかの問いそのものでもある。
だからこそ、焦る必要はない。迷って当然であるし、立ち止まることが悪いわけでもない。
それでもなお、少しずつでもいい。
自分の価値観と向き合い、自分なりの言葉で自分のキャリアを語れるようになったとき、きっとどこかで「この道でよかった」と思える瞬間が訪れるはずである。
本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いである。