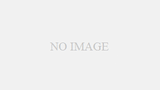はじめに|営業職で転職して年収を上げたいあなたへ
営業職として働いていると、ふとした瞬間に「このままで自分の年収は伸びるのだろうか」「転職すればもっと上がるのだろうか」と考えることはないだろうか。
同期や同世代の知人が転職でキャリアアップしている姿を見て、「自分も挑戦したほうがいいのか」「でも下がってしまったら怖い」と揺れる人も多い。
転職で「年収が上がる人・下がる人」の違いを知ることが大切な理由
私自身、これまで数百人規模の営業職の転職相談に携わってきたが、「転職で年収が上がる人」には明確な共通点があると実感している。一方で、そのパターンに当てはまらないまま動き出すと、年収を下げてしまったり、条件のミスマッチに苦しむことも少なくない。
本記事では、営業職が転職によって年収を上げるための“現実的なパターン”を整理し、さらに一足飛びではない上げ方、通過点となる業界の選び方まで具体的に解説していく。ここに書かれた内容は、私自身がキャリア支援の現場で見てきた“リアルなデータと事例”をもとにしたものだ。
「今のままでは先が見えない」「年収を上げたいがどう動くべきかわからない」と感じているあなたに、ぜひ参考にしていただきたい。読み終わるころには、自分がどのタイプに当てはまり、どんなステップで動くべきかのヒントがきっと見つかるはずである。
営業職からの転職で年収を上げる人の特徴4選
① 同業界での転職(30代までは可能性が高い)
年収を最も手堅く上げる方法は、やはり「同業界・同職種への転職」である。
これは一見シンプルだが、実際に多くの転職者が結果を出している“鉄板ルート”であり、経験値を最大限に活かせるステップでもある。
同業界への転職が有利な最大の理由は、即戦力評価が圧倒的に受けやすいことにある。
企業側にとって、同じ業界での経験を持つ候補者は「業界構造」「商習慣」「競合」「顧客層」などの暗黙知をすでに備えており、入社後のキャッチアップ期間を大幅に短縮できる。
これは採用リスクの低減にもつながるため、初めから給与レンジを上乗せして提示しやすい。
たとえば、
- 人材紹介営業 → 同じ人材系大手
- SaaS営業 → 同じSaaS企業
という動きは典型的である。こうした転職は、単に「規模の大きい企業に行く」というだけでなく、「現職で培った業界知識や人脈・成功事例を持ち込むこと」に価値が置かれる。
また、顧客ネットワークや営業スキルの“言語化”がしやすいのも強みだ。
たとえば「年間○社を開拓し、売上○%アップ」という数字はもちろん、「特定業界の意思決定プロセスに精通」「既存顧客リストを保有」「競合との差別化ポイントを熟知」といった“再現性のある経験”として面接で伝えやすい。この「再現性の高さ」が、同業界転職の年収アップ率を押し上げている。
私自身の支援経験でいえば、8割以上の方が年収アップに成功している。
しかもその多くが、年収だけでなく役職やポジション面でもステップアップを果たしている。
30代前半までであれば「即戦力+将来のマネジメント候補」として採用されるケースも多く、オファーの幅がさらに広がるのが実情だ。
ただし、同業界転職は“現職での実績”が重要になるため、「数字で示せる成果」「業界特有の知見」「顧客ネットワーク」のいずれかは必ず整理しておくべきである。逆に言えば、そこをしっかり固めておけば、最短かつ確実に年収を上げるチャンスを掴めるといえる。
② 経験値と年齢に対して給与が低い人の転職(20代がメイン)
20代前半〜中盤で、スキルや成果はあるのに給与が市場相場より低い人は、転職市場で“最も狙い目”と言ってよい層である。
現職での待遇が相対的に低い場合、転職によって一気に「相場」に引き上げられるため、年収アップの再現性が非常に高い。
この層が評価されやすい最大の理由は、「若さ×実績」という掛け算である。
企業は、20代の人材に対して「これからの伸びしろ」に大きな価値を見出しており、特に営業職で実績があれば、業界未経験でもポテンシャル採用の枠で高待遇を提示することが多い。
典型的な例としては、
- 中小企業 → 大手企業
- 中小広告代理店 → 大手人材紹介営業
- SaaS・人材・広告代理店・WEBメディア営業など、成長業界への転職
などが挙げられる。
私の支援経験でも、こうしたケースでは6〜7割の人が年収アップに成功している。
なぜ異業界でも上がりやすいのか。
それは、営業職のスキルが「無形商材」側に汎用性を持ちやすいからである。無形商材は課題ヒアリング力・提案力・顧客折衝力など、応用可能なスキルが多いため、企業も“未経験業界”のハードルを下げて即戦力として受け入れる傾向がある。SaaS・人材・広告代理店・WEBメディアといった業界はその代表格だ。
一方で注意点もある。たとえばメーカー系など有形商材中心の営業職は、もともと給与水準が高めなケースが多く、また専門性が“その商材に特化”していることが多い。結果として異業界に移っても同等の評価が得られず、給与アップにつながりにくい傾向がある。自分のスキルが“どこでも通用する型”なのか、それとも“今の業界専用”なのかを見極めることが重要である。
この層が転職に成功するコツは、「自分の実績と市場相場の差分」を把握し、それを武器に交渉することだ。たとえば「同じ年次の平均年収は○万円、私は現職で○万円」「顧客数・売上実績・表彰歴」といった具体的な数字を提示できれば、企業は「この条件で採らなければ競合に取られる」と判断しやすい。
まとめると、20代で経験値と年齢に対して給与が低い人は、転職市場で“ボーナスタイム”にいるようなものだ。早めに動くほど条件を引き上げやすく、次のキャリア選択肢も広がる。このチャンスを逃さずに、自分の市場価値を見極め、戦略的に転職活動を進めるべきである。
③ ポテンシャルに対して給与が低い人の転職(20代がメイン)
20代の中でも、新卒3年目〜5年目程度の人材は、転職市場で最も“伸びしろ”を評価されやすい層である。
スキルや実績は着実に積み上がっている一方で、給与はまだ伸び切っていないケースが多く、「ポテンシャル×実績」の両面評価で一気に年収を引き上げるチャンスがある。
企業側から見れば、この層は「教育コストをあまりかけずに戦力化でき、かつ将来のリーダー候補として育てられる」人材であり、特に営業職で実績を出している場合は「業界未経験でも採りたい」と判断されやすい。
典型的な例としては、
- 高学歴×新卒3年目×営業実績あり
- MARCH卒・中小メーカーで年収400万円 → 大手広告代理店で年収500万円
などが挙げられる。この層は書類選考さえ通れば、面接評価で高く評価されやすく、業界未経験でもチャンスを掴みやすい。
私の支援経験でも6〜7割の方が年収アップに成功している。
なぜこれほど評価が高いのか。それは、若さ・柔軟性・吸収力という3つの強みを企業が高く評価しているからである。30代に差し掛かると即戦力性やマネジメント力がより重視されるが、20代半ばまでであれば「今後の育成余地」に投資する意味が大きく、企業は「この人なら伸びる」と判断すれば破格のオファーを提示することもある。
また、ポテンシャル層は「未経験業界への転職」にも比較的強い。たとえばSaaSや人材、デジタル広告、コンサルといった成長業界は、商材や顧客の変化が激しいため、既存の経験よりも“適応力”や“思考の柔軟性”を重視する傾向がある。結果として、業界未経験者でも年収を引き上げながら転職できる土壌が整っている。
一方で、ポテンシャル層が見落としがちなのは「自分の価値の伝え方」である。単に「若いから」ではなく、「どんな実績・行動・思考特性があり、どう再現できるか」を具体的に示せるかが決定打となる。
たとえば「新規開拓率○%増」「受注単価○万円アップ」「顧客満足度○点向上」などの数字を提示できれば、企業は「今の年収より高くても採りたい」と判断しやすい。
要するに、“実績の棚卸し+ポテンシャルの言語化”ができれば、20代半ばの転職は一気に跳ねる。私の経験でも、この層は年収アップだけでなく、業界チェンジ・職種チェンジの成功率も高い。逆に言えば、このチャンスゾーンを逃すと、30代以降は「即戦力枠」としての競争が激化するため、条件交渉が難しくなる。
まとめると、ポテンシャルに対して給与が低い人は、転職市場における“旬のタイミング”にいる。若さと実績の掛け算が効くうちに、自分の強みを整理し、積極的に市場に出てみることが、年収アップとキャリア拡大の近道になるといえる。
④ インセンティブで稼ぐ会社への転職
固定給ではなく「インセンティブ(歩合給)」を軸に年収アップを狙う方法もある。これは他の3パターンとは少し性質が異なるが、実績次第では短期間で大きく年収を伸ばせる可能性を秘めている。特に「成果にコミットし、数字で自分を証明できるタイプ」にとっては非常に有効な戦略である。
このルートが年収アップにつながりやすい理由は、「成果がそのまま収入に直結する」構造にある。固定給主体の企業では、給与レンジはある程度決まっており、昇給には時間がかかる。しかし、インセンティブ重視の会社では、月次・四半期ごとの成果に応じて報酬が変動するため、早ければ入社初年度から高収入を実現できることも珍しくない。
典型的な業界としては、
- 保険営業
- 賃貸・売買不動産
- 中古品買取・リユース業界
などが挙げられる。これらは「個人営業」で顧客獲得件数や契約金額に応じて歩合が発生するモデルが多い。
私の支援経験では、5〜6割の方が年収アップに成功している。
一方で、固定給+インセンティブ型の給与体系には明確なリスクもある。
- 成果を出せなければ、固定給部分が低いために年収が下がる
- 季節変動や市況変化によって成果が安定しない場合がある
- 精神的プレッシャーやノルマの厳しさが大きい
つまり、この選択肢は「成果主義に強い人」「自己管理が得意な人」ほど向いている。自分の営業力に自信があり、数字を積み上げることが好きなタイプにとっては、年齢や経歴に関係なく短期間で高収入を実現する“抜け道”になり得るが、逆に安定志向の人には負担が大きい。
インセンティブ型の会社で成功するためのポイントは、「自分の営業スタイルとマッチする市場・商品を選ぶこと」である。高単価商材かつ成約率が高い市場、あるいはリピート契約やストック収益が見込めるモデルなど、成果が積み上がりやすい環境を選ぶことで、安定感と高収入を両立しやすくなる。
まとめると、インセンティブで稼ぐ会社への転職は、「即戦力として成果を出せる自信がある」「報酬とリスクを天秤にかけても挑戦したい」という人にこそ向いている戦略である。固定給主体の企業では到達できない年収レンジを短期で実現できる一方で、下振れのリスクもあるため、自分の志向性・生活スタイル・キャリアプランと慎重に照らし合わせることが成功への鍵となる。
営業職からの転職で年収を下げてしまう人の特徴とは?
「上記の4パターンに当てはまらない人は、もう年収アップは無理なのか?」――多くの人がここで諦めがちだが、実はそうではない。
ただし、正直に言えば“一足飛び”の年収アップはかなり難しい。これは、転職市場が「即戦力性」「再現性」「リスクヘッジ」を最優先にするためである。
一足飛びで高収入を狙う際の落とし穴
一足飛びで高年収を実現できる人は、以下のような“外れ値”に限られる。
- 圧倒的な実績や専門性を持ち、ポテンシャルがずば抜けて高い人
- 企業の採用ハードルが一時的に下がっているタイミングに偶然ハマった人
- その業界で突出した人脈や希少スキルを持つ人
要するに、狙って再現できるものではない。「運+圧倒的な実績」が必要になるため、ほとんどの人には再現性がない。
段階を踏んでキャリアを構築する考え方
しかし、段階を踏むことによって“結果的に大幅な年収アップ”を達成することは十分可能である。これはいわば“キャリアの乗り換え戦略”であり、私の支援経験でも再現性が高い。
一足飛びの年収アップが難しいとしても、「戦略的に通過点を設ける」ことで、最終的には大幅な年収アップを実現したケースがいくつもある。ここでは典型的な3つのパターンを紹介する。
ケース1:法人営業 → 中小SaaS企業CS → 大手SaaS企業CS
- 年収推移:400万円 → 350万円 → 560万円
最初は法人営業として培ったヒアリング力や提案力を活かし、IT系CS(カスタマーサクセス)職に転身。初めは年収が下がったものの、IT・SaaS業界特有のカスタマーサクセスの知見を積むことで市場価値が急上昇し、最終的に大手SaaS企業のCSポジションで年収560万円に到達した例。
ポイント:「短期的な年収減を許容し、無形商材×成長業界の経験を取りに行く」ことが、次の大幅アップにつながった。
ケース2:メーカー → 大手人材営業 → 採用コンサル
- 年収推移:600万円 → 550万円 → 700万円
メーカーでの営業経験をベースに、まずは人材業界に移って採用や組織構築の知見を深め、その後コンサルティングポジションにシフト。人材・組織開発という高単価領域で提案力を活かすことで年収700万円に到達。
ポイント:「有形商材 → 無形商材 → コンサルティング」というステップで“業界横断的な知識”を武器に変え、市場価値を一段ずつ積み上げた。
ケース3:個人営業 → 広告代理店 → ネットメディア
- 年収推移:500万円(インセンティブ込み) → 400万円 → 630万円
個人営業で培った“売る力”を、まずは広告代理店で法人向けの提案スキルに昇華させ、その後ネットメディア企業へ移ってデジタル広告・無形サービス領域にポジションを確立。最終的に年収630万円に到達した例。
ポイント:「営業の汎用スキル+デジタル領域の知見」を掛け合わせることで、短期的な年収減を乗り越え長期的な高収入を実現した。
一度年収が下がっても、次の転職で大幅に年収を上げるコツ
- 短期的な年収減を“投資”と捉え、市場価値を上げる経験を優先している
- 業界や職種の“汎用性が高いスキル”を取りに行く
- 2ステップ目で「成長業界・無形商材」に移っているため、3ステップ目で評価が跳ねる
つまり「谷を恐れずに経験を積む」ことが、次の飛躍の布石になるということだ。短期的な損失を許容できる人ほど、中長期でキャリアの選択肢が広がり、結果的に高年収に近づいていく。
まとめ|一足飛びではない年収の上げ方のコツ
- 市場価値を伸ばせる「通過点」職種を選ぶ
いきなり高年収を狙うより、将来性のある職種・業界で経験を積むほうが結果的にリターンが大きい。 - 「無形商材・成長業界」での経験を取りに行く
無形商材は汎用性が高く、成長業界は次の転職時に評価されやすい。 - 3年以内に“実績を言語化できる成果”を作る
「どこでも通用する実績」を持っておくと、次の転職時に交渉力が格段に上がる。
この3ステップを意識すれば、たとえ一度は年収が下がっても、その後の転職で大幅に引き上げることが可能になる。
年収を上げるための通過点とすべき業界の特徴と例
転職で年収を上げるには、「いきなり高収入ポジションに飛び込む」のではなく、“通過点”を意識してキャリアを構築することが極めて重要である。特に未経験領域や無形商材に挑戦したい場合、以下の3つの業界は“市場価値を一段上げる中継地点”として非常に有効である。
① 人材紹介業界
- 特徴: 未経験から無形商材の法人営業に進むうえで間口が広く、営業職としての基礎を磨く環境が整っている。
- メリット: 様々な業界・職種・企業規模の情報にアクセスできるため、「市場全体の地図を手に入れる」ことができる。結果、自分自身のキャリア設計や“どのように自分を魅せるか”というスキルが自然と身につく。
- 次のキャリアへの強み: 無形商材営業×法人顧客対応力がセットで鍛えられるため、SaaS・コンサル・広告など「提案型・課題解決型」のポジションへ移る際に評価されやすい。
ポイント: 「まずは人材紹介で無形営業を覚え、その後SaaSやコンサルへジャンプ」というキャリアは、再現性が高く成功例も多い。
② SaaS業界
- 特徴: 成長スピードが速く、かつ企業数・ポジション数も多いが、その分競争倍率が高い。ただし対策次第では未経験でも十分チャンスがある。
- メリット: 一度SaaS企業に入れば、その経験は“引っ張りだこ”になる。SaaS業界は横への展開がしやすく、次の転職で条件を引き上げやすいのが特徴。経験者への待遇も比較的良く、昇給・昇格スピードも速い。
- 次のキャリアへの強み: デジタルプロダクトの販売経験、カスタマーサクセス、データ活用・LTV改善など、現代的な営業・マーケティングスキルが一気に身につく。これらはどの業界でも求められているため、次の転職で評価されやすい。
ポイント: 「とにかくSaaS業界で一度経験を積む」こと自体が強力なブランドになり、市場価値の底上げに直結する。
③ 広告代理店・ネットメディア業界
- 特徴: 無形商材かつ多様な顧客業界に携わるため、営業力・企画力・提案力を総合的に鍛えられる。未経験からの入りやすさは中〜上だが、代理店は志望動機や面接対策をしっかり練らないと通過が難しい。
- 広告代理店: 多くの業界のクライアントに提案するため、「課題解決型の営業力」が磨かれる。提案単価やプロジェクト規模も大きく、スピード感のある環境で成長できる。
- ネットメディア: 自社のメディアを持っている企業が多く、志望動機を作りやすい一方で、データ分析力・企画力・マーケティング思考など“自頭”が求められる。結果として「どこでも通用する企画力・編集力・運営力」を身につけやすい。
- 次のキャリアへの強み: SaaS・コンサル・自社サービスのマーケティングなど、企画・営業・CSのどの方向にも展開可能。
ポイント: 「代理店・メディアで広い経験を積み、その後特化型SaaSや自社プロダクトへ移る」ことで、ポジションと年収を引き上げやすい。
まとめ
これら3つの業界はいずれも、「市場価値を高める経験が手に入る」「スキルの汎用性が高い」「次の転職で評価されやすい」という共通点がある。
短期的に見れば年収が横ばい〜微減になることもあるが、長期的には大幅な年収アップとキャリアの広がりにつながる“通過点”となる。
「どの業界にいるか」でキャリアの伸び方は大きく変わる。成長業界・無形商材・多様な顧客との接点を意識して選ぶことで、次の転職で一気に跳ねるチャンスをつかむことができる。
さいごに|営業職が転職で年収を上げたいなら“情報+戦略”が武器になる
ここまで「転職で年収が上がる人の特徴」や「一足飛びではない上げ方」「上げるための通過点となる業界」について解説してきた。おそらく読者の多くが「自分はどこに当てはまるのか」「どんな順路でキャリアを積むべきか」と考えながら読んでくださったのではないだろうか。
私自身、何百人もの営業職のキャリア支援を行ってきたが、「自分の市場価値を客観的に把握している人ほど、転職活動がスムーズで失敗しない」という共通点がある。
逆に「なんとなく今の環境が嫌だから」と動き始めると、条件を下げてしまったり、本来狙えるポジションを逃したりするリスクが高い。
その意味で、「今の自分の立ち位置を第三者視点で見てもらう」ことが極めて重要である。特に成長企業やSaaS、人材、広告などの分野に強いエージェントは、最新の年収相場・求人動向・選考傾向を常に把握しているため、「どの業界・職種にどの順番で移ると年収が伸びるか」という戦略を具体的に描く手助けをしてくれる。
もしこの記事を読んで「自分が上がる人かどうか知りたい」「どんな通過点が適切か整理したい」と思ったら、以下の成長企業特化型の転職エージェントにまず相談してみることを強くおすすめしたい。
相談だけでも構わないし、むしろ早く動くほど選択肢は広がる。情報を集め、比較し、自分の価値を客観的に測るだけでも、次のキャリアに対する安心感が違ってくるはずである。
転職は一人で闇雲に挑むよりも、情報・戦略・客観性を持って進めるほうが何倍も成功確率が高い。ぜひ、あなた自身の可能性を広げるために、まずは一歩踏み出してみてほしい。