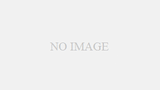はじめに|「仕事を辞めたい」と感じるあなたへ
私は転職エージェントとして、これまで数えきれないほど「仕事を辞めたい」という悩みを抱えた方と向き合ってきた。
しかし、それは他人ごとではない。実のところ、私自身も過去に何度も同じ思いを抱き、心の中で「辞めたい」という言葉を繰り返した経験がある。
そのたびに頭をよぎったのは――「辞めた後、自分は大丈夫だろうか?」という、まだ見ぬ未来への漠然とした不安である。
冷静に考えれば、これは当然のことだ。
いま自分がうまくいっていないからこそ、未来に楽観的なイメージを描くのは難しい。過去の失敗や停滞感が心を縛り、「また同じことが繰り返されるのではないか」と疑ってしまう。
だからこそ、多くの人は「今の痛み」と「将来の不安」とを天秤にかけ、結果として“今のつらさを受け入れてしまう”選択をしてしまうのだろう。
おそらく、この記事を読んでくれているあなたも、そんな葛藤の最中にいるのではないだろうか。
「辞めたい」と心が叫んでいるのに、同時に「辞めてはいけない」という声が頭を離れない。まさに板挟みのような苦しさを抱えているはずだ。
私は、この文章を通じて「あなたの気持ちは間違っていない」とまずは伝えたい。
そして、そのうえで――少しでも気持ちが楽になり、次の一歩を考える余裕が持てるように、仕事がつらいときのマインドセットや具体的な整理の仕方をお伝えしていこうと思う。
1.仕事がつらい・辞めたいと思う感情を肯定しよう
「仕事を辞めたい」と思う気持ちは、決して珍しいものではない。
むしろ、多くの人が一度は胸に抱く自然な感情である。
理由はさまざまだろう。新しい挑戦を求めてポジティブに退職を考える人もいるかもしれない。だが、まずお伝えしたいのは――「多くの人にとって、環境を変えたい理由はネガティブなものが多い」という事実である。つまり、あなただけが特別に弱いわけでも、甘えているわけでもないのだ。
私自身も、これまで本気で「辞めたい」と思ったことが何度もある。実際に転職も経験している。
特に新卒で入社した会社では、今思い返しても心がざわつく経験をした。いわゆる“上司ガチャ”が悪かったのである。モラハラまがいの指導は日常茶飯事で、得意先や他社の社員がいる場で大声で怒鳴られることもあった。人格否定の言葉を浴びせられることも一度や二度ではなかった。
当時の私は完全に委縮してしまい、何をするにも萎縮した態度になっていたと思う。すると、それが上司の目には「消極的で頼りない部下」と映ったのだろう。怒られる頻度はさらに増え、負のサイクルは日を追うごとに強く、そして速くなっていった。その感覚は、今でも鮮明に覚えている。
おそらく、初めて「仕事を本気で辞めたい」と思ったのはこの時期だったはずだ。
――そして、そこから学んだことがある。
それは、「そもそも仕事とは、誰にとってもつらさを伴うものだ」ということである。
けれども、その“つらい”という感情を抱けるのは、あなたが自分を大切にできている証拠でもある。限界を迎えている自分の心や体が、きちんと「SOS」を出してくれているのだ。
だからこそ、まずはここまで頑張ってきた自分を認めてあげてほしい。
「よくやってきたな」と声をかけてほしい。
そして、苦しいと感じた自分の心と体に対して「気づかせてくれてありがとう」と言ってあげてほしい。
あなたが感じている「辞めたい」という気持ちは、弱さではなく――“自分を守る力”なのだ。
2.仕事を辞めたい・つらいときのマインドセット
「仕事を辞めたい」と思うとき、多くの人の頭を支配するのは――「辞めて本当に大丈夫なのだろうか?」という将来への漠然とした不安ではないだろうか。
だが、結論から伝えたい。実は、辞めてしまっても問題ないことの方が圧倒的に多いのである。
なぜなら、未来は良くも悪くも予測できないからだ。
たとえば、仕事が順風満帆で「次のステップだ」と意気揚々と辞めても、新しい会社で思うように力を発揮できない人もいる。逆に、心身が限界に近づき「とにかくこの場から逃げたい」とネガティブな理由で辞めたにもかかわらず、転職先で自分に合った環境を見つけ、以前よりも生き生きと働けるようになる人もいる。
つまり、今がポジティブであろうとネガティブであろうと、未来には常に不確実性がつきまとう。辞めなければ不安、辞めても不安――その「不安」自体がなくなることはないのだ。だからこそ、辞めるかどうかを「未来の確実性」によって判断しようとすること自体が無理なのである。
では、なぜそのように言えるのか。これは無意識的にはみんなが感じていることであると思うが、
「私たちが直面している出来事を構成する要素の多く」は「外的要因」であり、「ほとんどが自身でコントロールできない事」の連続の結果なのである。
にもかかわらず、多くの人はそれをうまく言語化できないだけである。
少し噛み砕いて言えば――「今の状況は、あなたの実力とは無関係に“運”の要素によって形づくられている部分が大きい」ということだ。
考えてみてほしい。
もし、あなたの隣にいる優秀な先輩が別のチームに配属されていたら? もし、その先輩がそもそも別の会社に就職していたら? あなたが「比較されて苦しい」という状況自体、発生していなかったかもしれない。
その配属や人事の流れを、あなたは事前にコントロールできただろうか?
答えは、当然「できない」である。そう、あなたが今苦しんでいる理由の一部は、ただ単に「運が悪かった」だけなのだ。
もちろん、その逆も起こる。
次に入社した会社では、あなたがこれまで当たり前にやってきた業務が「喉から手が出るほど欲しいスキル」として評価されることもある。しかもそれは、あなたの転職活動のタイミングと、その会社が人を求めるタイミングが偶然重なった――ただそれだけのことかもしれない。
要するに、「辞めればうまくいく」「辞めなければうまくいかない」といった答えは、今この瞬間には出せない。未来を完璧に予想することなど不可能だからだ。
だからこそ、過度に不安を抱える必要はない。
「辞めてもいい」と考えてよいのである。
むしろ、「辞める・辞めない」を決める基準は“未来の正解”ではなく、“今のあなたがこれ以上傷つかずに生きていけるかどうか”であるべきなのだ。
3.会社を辞めたい理由の整理と対処法
さて、ここからは「辞めたい理由の整理」について考えていきたい。
なぜなら、感情のまま「辞めたい」と思っているときに、それを言葉にして整理するだけで対処の糸口が見えてくることが多いからである。
①人間関係の問題
辞めたい理由の中でも、もっとも多いのはやはり 「人間関係」 の問題ではないだろうか。
特に多いのが「上司・先輩」との関係性である。
「上司からいじめられている」――こうした悩みを抱える人は決して少なくない。
私自身も先に述べた通り、新卒時代は強烈なモラハラを受けた。人格を否定され、日々自分の存在価値が削られていく感覚に押し潰されそうになった。あの時期の苦しさは今でも忘れることができない。
では、人間関係が理由で辞めたくなる場合、どのように整理すればよいのか。ここでは、あえて2つのパターンに分けて考えてみたい。
先輩・上司が「実はいい人」だったパターン
「そんなわけない」と思う人もいるだろう。だが、一度だけ立ち止まって考えてみてほしい。
人は、耳の痛いことを言われると本能的にその相手を嫌いになる傾向がある。けれども、その言葉が“本当にあなたの成長を願っての指摘”だったとしたらどうだろうか。
上司や先輩は、あなたが目指すキャリアのために、あえて厳しく接している可能性もある。あるいは、会社の中で求められる基準に到達していないあなたを守るために、今あえて「鬼」となっているのかもしれない。
もちろん、全員がそこまで深い意図を持っているわけではない。だが、もしあなたが素直に声を上げれば「そこまで嫌だったのか」と態度を和らげてくれる人もいる。
そうであれば、その環境はむしろ恵まれていると言えるだろう。厳しい関係性の裏側に“あなたを想う気持ち”が隠れている場合、それはあなたにとって将来プラスに働く環境かもしれない。
先輩・上司が「合わない人」だったパターン
しかし、多くの人が直面しているのはこちらではないだろうか。
いわゆるハラスメント上司や、悪意をもって人を傷つけるタイプである。こうした存在は極めて卑劣だ。なぜなら、仕事に必要のない感情であなたの心を蝕んでいるからである。
この場合の対処法は状況によって変わる。
もし周囲に味方がいるなら、協力を得つつ「証拠を残す」ことを意識してほしい。録音機器やスマホ、あるいは私も使ったことのある「録音機能つきボールペン」でもよい。証拠を持ったうえで、人事や信頼できる別の上司に相談する。これは有効な手段である。
また、周囲からも嫌われているタイプの上司であれば、思い切って通報することで周囲が一斉に味方になるケースもある。むしろ、そうした人間を排除できる機会になるかもしれない。
だが、さらに厄介なのは“立場”を盾にあなたをピンポイントで狙う上司である。周囲が味方になりにくい場合、証拠を集めても解決が難しいことがある。
この場合、私は「辞める」という選択がもっとも合理的だと考えている。理由は3つある。
- そのような人間が評価される会社は、上層部も同じ体質である可能性が高い。 出世すればするほど、より人間性の歪んだ人と対峙しなければならない未来が想像できる。
- 辞めることで迷惑を被るのは会社側である。 あなたが業務を担っている限り、辞めればその負担は上司や会社に返っていく。むしろ一番困るのは彼らだ。
- その会社ではあなたが正当に評価されない可能性が高い。 合わない価値観の人間が評価されている環境で、あなたが報われる日は来ない。であれば、あなたを正しく評価してくれる会社を探す方が健全である。
「人間関係」で辞めたいと思う気持ちは弱さではなく、むしろ自然な反応だ。
そして整理してみれば――耐えるべき環境なのか、それとも離れるべき環境なのかが見えてくる。
その整理こそが、次の一歩を踏み出すための大事なプロセスになるのである。
②成長できない
「成長できていない」と感じることも、会社を辞めたい理由として非常に多いのではないだろうか。
任されている業務レベルが低すぎて物足りなさを覚える場合もあれば、そもそも担当しているポジション自体がスキルアップにつながりにくいケースもある。
特に多いのは、社会人2年目から3年目にかけてである。ある程度の業務をこなせるようになり、同じことの繰り返しに慣れてしまう時期。成長曲線が一旦なだらかになる時期でもあり、多くの人が「このままでいいのだろうか」と不安を抱く。
では、この「成長できない」という悩みにどう向き合えばいいのか。ここでも2つのパターンに分けて考えてみたい。
キャリアの方向性が明確な場合
もしあなたが「将来はこうなりたい」というキャリアをある程度描けているのであれば、そのイメージから逆算して今必要なスキルを考えるべきである。
そのスキルが今の会社で身につかないと分かっているのであれば、早急に異動を願い出るか、転職を視野に入れる方が良いだろう。
キャリアの軸がはっきりしている人にとって、時間は最大の資産である。
今の業務に留まることで未来の可能性が狭まるのであれば、環境を変える決断は決して逃げではなく「前進」である。
キャリアの方向性がまだ曖昧な場合
一方で、「自分が何を目指したいのか、正直よく分からない」という人も多いはずだ。むしろ、このケースの方が一般的である。
この場合に必要なのは、キャリアの言語化である。つまり――「人生における仕事の役割とは何か?」「働くことで何を叶えたいのか?」を少しずつ言葉にしていく作業である。
ただし、この作業は簡単ではない。何度も自問自答を繰り返し、時間をかけてようやく輪郭が浮かび上がってくるものだ。
よくある転職失敗の原因のひとつに「漠然とした理由での転職」があるが、その背景には「今の業務に慣れてしまって飽きてきた」というだけで動いてしまうケースが多い。これは非常に危険である。
だからこそ、焦る必要はない。むしろ「自分にとっての成長とは何か」をできるだけ言語化した状態で転職をする方が、納得感のある選択につながるのである。
言語化を一人で行う難しさ
とはいえ、言語化は一人で行うには難しい側面がある。
理由はシンプルで、自分の頭の中だけで考えていると、どうしても思考が堂々巡りになってしまうからだ。
だからこそ、第三者の力を借りるのが有効である。
特に、転職エージェントを「求人紹介」ではなく「言語化の手伝い」として使うのは非常に意味がある。自分では気づけない強みや価値観を引き出してくれる存在として活用するのだ。
成長できないという悩みは、裏を返せば「もっと成長したい」という前向きな欲求の表れでもある。
であれば、その思いを無駄にせず、焦らず丁寧に言語化しながら進めていけばよいのである。
③働く環境
「土日は休みたい」「残業が多すぎてつらい」「転勤だけはどうしても避けたい」――こうした理由もまた、辞めたいと思う大きな要因のひとつである。誰にとっても「働く環境」は仕事の満足度を大きく左右する。
まず最優先に考えてほしいのは、あなたの体調面である。
頑張ることは素晴らしい姿勢だが、体や心を壊してしまっては元も子もない。得られるものはなく、むしろその後の人生に大きな影響を残してしまう。だからこそ、「無理をしてまで続けるべきではない」ということを、最初に強くお伝えしたい。
余裕がまだある場合
もし「今すぐ限界ではないが、このままでは長く続けられそうにない」と感じているのであれば、まずは現職にとどまりながら転職の準備を始めるとよい。具体的には、キャリアの言語化から始めるのをお勧めする。
特に若いうちは「ワークライフバランス」よりも「成長機会」を優先することは、決して悪いことではない。もちろん限度はあるが、成長のために一定の負荷を引き受けることはむしろポジティブな選択である。
私自身、かつて月に80〜100時間ほど残業をしていた時期がある。大変ではあったが、そのときに培ったスキルや経験はいま確実に自分を支えている。とはいえ、これはあくまで私の上限であり、人によって許容量は必ず異なる。だからこそ、無理をしてはならないのだ。
すでに限界を感じている場合
おそらくこの記事を読んでいる方の中には「もうすでに今の働き方に限界を感じている」という人も多いだろう。その場合、まずやるべきことは上司への進言である。
人にはそれぞれキャパシティがあり、その大きさは人によって違う。与えられたものを処理できない自分に抵抗感を覚える人もいるだろう。私自身もそういうタイプであった。しかし、視点を変えて考えてみてほしい。
顧客や会社の立場から見て、疲弊した担当者に任されることが本当に幸せだろうか? 疲れ切ったあなたでは、顧客に最大限の価値を届けられないかもしれないし、会社としても売上や成果を取りこぼす可能性がある。
つまり、あなたが「もう無理だ」と感じているのは、わがままではなく合理的なSOSなのである。
だからこそ、まずは業務量を減らし、回る状態を作ることが重要である。そこから質を高め、質が上がった段階で少しずつ業務量を増やしていく。このサイクルを繰り返すことで、無理をせずとも顧客や会社へ100%の価値を発揮できるようになっていくはずだ。
それでも改善されない場合の行動ステップ
とはいえ、現実的には「業務を減らしてもらえない」「忙しすぎて転職活動の時間が取れない」というケースも少なくない。そんなときは、段階を踏んだ転職活動を意識してみてほしい。
- 履歴書・職務経歴書を作成する
これはAIを使えば1時間で終わる。ここまでできたら、まずは「今日はここまで」と区切ってよい。 - 自分のキャリアや価値観に合う業界・職種を探る
AIに質問しながら、1日10分、1週間程度かけて考えるだけでよい。この段階では深掘りしすぎず「方向性の種」を見つけることが大切だ。 - 方向性が固まったらエージェントに連絡する
あとはプロに任せることで、自分一人では気づけなかった可能性が見えてくる。 - 転職活動を開始する
可能であれば現職と並行して進めるのがよいが、どうしても難しいなら退職してからでも構わない。ただし収入面だけは計算しておくこと。退職から半年以上経つと企業が気にするケースもあるため、「辞めると同時に活動が始まっている状態」を意識するとよい。
「働く環境が合わない」と感じることは弱さではなく、むしろ健全な自己防衛である。
あなたがすでに全力で頑張っているからこそ、限界に達してしまったのだ。
だからこそ、その気持ちを否定する必要はない。むしろそれをきっかけに、次のステージへ進むための準備を始めていけばよいのである。
④評価されない
そして最後に挙げたいのが「評価されない」という理由である。
これは人間関係や業務内容と同じくらい、多くの人が抱える深い悩みだ。
「頑張っているのに認められない」
「成果を出しているつもりなのに正しく評価されない」
こうした感覚は、あなた自身の努力が足りないからではなく、むしろ環境や仕組みの側面が大きい。
評価制度が不透明であったり、上司の主観で判断されることが多かったりするのは、決して珍しいことではない。あなたの価値や強みが正当に伝わっていないだけで、決して“あなたに価値がない”わけではないのだ。
もし「評価されない」という悩みに強く共感したのであれば、一度こちらの記事も読んでみてほしい。具体的な整理の仕方や考え方がまとまっているので、あなたのモヤモヤを言語化する助けになるだろう。
さいごに|「辞めたい」はあなたの可能性を広げるサイン
ここまで「人間関係」「成長できない」「働く環境」「評価されない」といった辞めたい理由を整理してきた。
おそらく、この記事を読み進めながら「ああ、自分も同じだ」と心に刺さる部分があったのではないだろうか。
まず伝えたいのは――あなたが感じている「辞めたい」という気持ちは決して間違っていないということだ。
それは甘えでも弱さでもなく、あなたの心と体が「今のままでは持たない」と教えてくれている大切なサインである。
ただし、辞めたいという気持ちに寄り添うだけでは未来は変わらない。
大切なのは「辞めたい理由を整理し、次の一歩を考えること」である。
そのときに必要なのは、あなた一人で抱え込まず、信頼できる伴走者を持つことだ。
そこで以下のエージェントサービス活用を是非おすすめしたい。
ただ求人を紹介するだけではなく、「あなたの辞めたい理由」を丁寧にヒアリングし、キャリアの言語化から一緒に進めてくれる。自分では気づけなかった強みや価値観を引き出し、環境選びの軸を一緒に磨いてくれるのだ。
私自身、転職を経験して強く感じたことがある。
「正しい努力をしていても、環境が合わなければ報われない」という現実だ。
逆に、環境を変えた途端に同じ自分でも評価され、成長の機会に恵まれることは珍しくない。
だからこそ、一歩を踏み出す勇気と、信頼できるパートナーの存在が重要になる。
もし今の職場で悩みを抱えているのなら、まずは登録してみてほしい。
そこから始まる会話が、あなたの新しい未来を開くきっかけになるはずだ。
あなたが自分らしく輝ける場所は、必ず存在している。
そしてその扉を開くのは、他の誰でもなく、あなた自身の行動である。