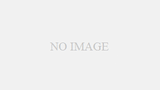転職エージェントをしていると求職者の方からよく言われることがある。
それは「市場価値を上げたい」という内容である。ただ、市場価値というワードの本質的意味を理解して使っている方は果たしてどれだけいるだろうか?
この記事では市場価値への正しい理解を持ったうえでどのようにして転職で活かしていくか?を伝えたい。
はじめに
「これからの時代は“市場価値”がますます重要になる」と耳にしたことはないだろうか。
実際に私自身も、新卒で入社したメーカーで働いていた頃、漠然と「市場価値を上げなければならない」という焦りから転職活動を始めた経験がある。
しかし、振り返ってみると当時の私は「市場価値」という言葉を深く理解していたわけではなかった。ただなんとなく「高いほうが良いものだろう」というイメージを抱き、その実態を曖昧なままにしていたのである。おそらく多くの方も同じように、市場価値という言葉を“ぼんやりとした不安”とセットで考えているのではないだろうか。
ここで一つ、強調しておきたいのは「市場価値は万能ではない」という点である。市場価値を高めれば必ずしもすべてが解決するわけではなく、キャリアの選択肢や働き方次第で価値の見え方は大きく変わっていく。だからこそ、まずはその言葉が意味する本質を理解することが欠かせない。
この記事では、単に「市場価値を上げるべきだ」と煽るのではなく、
- 市場価値とは何か
- どのようなメリット・限界があるのか
- 実際に市場価値を上げるための転職戦略
- 具体的におすすめできる業界・職種
といった流れで丁寧に解説していく。
「何となく市場価値を高めたい」と考えている方が、読後には“自分に合ったキャリアの上げ方”を具体的に描けるようになることを目指している。
そもそも市場価値とは
そもそも「市場価値」とは何なのだろうか?
結論から言えば、それは転職市場における“需要と供給のバランスを表す指標”である。
転職市場には、当然ながら「働きたい」と考える転職希望者と、「採用したい」と考える企業が存在している。
採用企業の求人数(需要)に対して、転職希望者数(供給)が少なければ、その分だけ一人ひとりの希少性は高まり、市場価値は上がる。逆に、同じポジションに多くの候補者がひしめき合えば、企業から見た「替えのきく存在」になりやすく、市場価値は低く見積もられてしまう。
つまり市場価値とは、
- 転職というマーケットの中で相対的に判断される指標であること
- “ある時点”における需要と供給の関係によって変動するものであること
この2点を押さえることが重要である。
ここで少し立ち止まって考えてみてほしい。
「市場価値を上げれば一生仕事に困らない」と思っていた方からすると、この事実は少しショックに感じられるかもしれない。実際、私自身もかつては同じように“市場価値さえ高めればキャリアは安泰だ”と考えていた時期があった。しかし現実には、市場価値は永続的に保証されるものではなく、数年単位で大きく変化する可能性がある“流動的な価値”なのだ。
たとえば、かつては引く手あまただった職種が、テクノロジーの進化や産業構造の変化によって一気に需要を失うこともある。逆に、ほとんど注目されていなかった分野が、数年後には「高年収・高需要」の花形ポジションに変わることだって珍しくない。
だからこそ大切なのは、一度市場価値を高めて終わりではなく、“高くあり続ける状態”をいかに維持できるかである。これは、キャリアを積む上で避けて通れない視点だ。
では、どうすれば市場価値を上げ、さらに高くあり続けることができるのか?
次の章では、そのための具体的な戦略について掘り下げていきたい。
市場価値を上げるための転職戦略
では、市場価値を上げ、さらに上げ続けるためにはどうすればよいのだろうか。
大きく分けると、その答えは次の2つに集約される。
- 「希少性と難易度が高い職種を選ぶこと」
- 「法人向けで、世の中からの需要が高まっている業界であること」
このどちらかに当てはまるかどうかが、市場価値を大きく左右する分岐点になる。
1. 希少性と難易度が高い職種を選ぶ
市場価値の基本原理は「希少性」である。
他に代わりが効かない人材であればあるほど、企業から声がかかりやすく、年収や待遇も高まりやすい。典型的な例がITエンジニアだ。
ただし注意したいのは、希少性だけでは不十分だということ。
どんなにニーズがあっても、数年後に同じスキルを持つ人材が一気に増えれば、相対的な価値は下がってしまう。ここで重要になるのが「難易度」という要素である。
たとえばITエンジニアの中でも、単にプログラムを組むだけでなく、
- システム全体の構成や要件を定義する「上流工程」
- 開発後に品質や動作を検証する「下流工程」
といった工程が存在する。この中で特に重宝されるのは「上流工程」を担えるエンジニアだ。なぜなら、抽象度の高い課題を整理し、システム全体を設計できる人は限られており、誰もが簡単に真似できる仕事ではないからである。
つまり、参入障壁が存在する職種を選ぶことが、長期的に市場価値を維持するカギになる。希少性が高く、かつ難易度の高いスキルを持っている人材は、企業から「ぜひ欲しい」と思われ続ける存在になれるのだ。
2. 法人向けで需要が高まっている業界を選ぶ
もう一つの重要な視点が、「法人向けかつ需要が高まっている業界」を選ぶことである。
「需要が高まっている業界を選ぶべき」という点は直感的に理解しやすいだろう。需要が高い=困っている顧客が多いということであり、その分だけ人材ニーズも強いからだ。
では、なぜ「法人向け」が良いのか。
理由はシンプルで、法人営業の場合、取引先も企業であるため、自分の顧客そのものがキャリアの次の選択肢になるケースが多いからである。
例えば、人材紹介会社で法人営業を経験した人が、取引先である「企業の人事担当者」側へ転職するケースは珍しくない。これは、法人営業で培った知見や経験がそのまま顧客企業で求められるためだ。
つまり、法人向けの成長業界で働けば、
- 業界自体の成長によって需要が膨らむ
- 顧客側からも声がかかりやすい
というダブルのメリットがある。結果として、キャリアの選択肢が広がりやすく、市場価値も自然と高まり続けるのだ。
戦略のまとめ
理想を言えば「希少性と難易度が高い職種」かつ「法人向けで需要が高まっている業界」の両方を満たせれば文句はない。
しかし、片方を満たすだけでも市場価値を高めるには十分だといえる。
キャリアにおいて大切なのは、「いかに努力してスキルを積むか」ではなく、努力が正しく評価される市場を選ぶことである。正しい土俵に立ち、戦略的に動くことが、市場価値を上げ続けるための最短ルートなのである。
市場価値が高い代表的な業界・職種
ここまで「市場価値を上げるための考え方」を整理してきた。では、実際にどの業界や職種が、
- 「希少性と難易度が高い職種を選ぶこと」
- 「法人向けで、世の中からの需要が高まっている業界であること」
に当てはまるのだろうか。ここからは具体的に見ていこう。
希少性と難易度が高い職種
まずは「希少性」の観点から。
希少性とは「そもそものポジション数が少ない」ということ。わかりやすい例はマネジメント層だ。
たとえば、あなたのチームには複数のメンバーがいても、直属の上司は一人しかいない。この構造はどんな組織にも共通しており、管理職やマネジメント職は常にポジションの椅子が限られている。だからこそ、一度マネジメント経験を積めば、どの業界でも転職市場で高く評価されやすい。
また、マネジメント以外にも「本部機能」と呼ばれる職種は希少性が高い。具体的には、
- 法務・税務:そもそもの職種絶対数が少ないためマーケットに出たら引く手数多となる。
- 商品企画/サービス企画:事業の方向性を決める“上流工程”を担う。
- デジタルマーケター:データ分析や広告運用など専門スキルの習得難易度が高い。
- 中途採用人事:人材獲得競争が激化する中で企業の生命線を担う。
これらは希少性が高いだけでなく、業務の難易度も高いため、長期的に市場価値を維持しやすいポジションといえる。
法人向けで需要が高まっている業界
次に「需要が高い業界」を見ていこう。
最もイメージしやすいのはIT業界である。特にSaaS(クラウドサービス)は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れを背景に、ここ数年で急激に需要が拡大している。企業の生産性向上やデータ活用のためにSaaSを導入する企業は年々増えており、業界全体として“伸びしろ”が大きい。
そのほか、法人向けで需要が高まっている業界としては、
- 広告代理店:デジタル広告市場の拡大に伴い、広告運用の知見を持つ人材は不足している。
- 人材紹介:労働人口減少により、採用課題を抱える企業が増えており法人営業のニーズが大きい。
- M&A仲介:中小企業の事業承継需要が増加し、専門知識を持つ人材が重宝される。
- コンサルティング:経営課題解決に直結するため、常に高い需要がある。
これらの業界は、法人営業やフロント職として経験を積めば、将来的に顧客側(=取引先企業)へのキャリアステップが開かれるケースが多い。つまり、「法人×需要が高い業界」で働くこと自体が、市場価値を上げるための布石になるのである。
まとめ
- 希少性と難易度の高い職種(マネジメントや専門職)
- 法人向けで需要が高まっている業界(SaaS、人材、広告、M&A、コンサル)
このどちらかに属するキャリアを選ぶことで、あなたの市場価値は確実に上がる。
さらに、両方を満たす選択ができれば、他の候補者とは一線を画す存在となり、転職市場で「引く手あまた」の状態を築けるだろう。
さいごに
ここまで「市場価値」という言葉の本質から、具体的に価値を高める戦略、代表的な業界・職種までを解説してきた。
振り返ってみると、
- 市場価値とは、あくまでその時点の需要と供給で決まる流動的なもの
- 上げ続けるためには、希少性×難易度が高い職種や、法人向けで需要が伸びている業界を選ぶことが大切
- 特に「マネジメント・本部機能・IT・SaaS・人材・コンサル」などは長期的に市場価値を高めやすい
ということがお分かりいただけたはずである。
ただし、ここで多くの方がぶつかる壁がある。
「頭では理解できても、自分にとって本当に合う選択肢はどこなのか?」
「今のスキルをどう活かして市場価値を上げられるのか?」
という悩みである。
これは、自分一人で考えても答えが出にくい領域だ。
なぜなら、転職市場のトレンドや、成長産業の情報は常に移り変わるため、最新の市場感を把握しているプロと対話することが最も効率的だからである。
そこでおすすめしたいのが、成長企業特化の転職エージェントである。
成長フェーズにある企業は、新しい役割やポジションが次々と生まれるため、個人の市場価値を伸ばすチャンスにあふれている。そうした企業との接点を持てることは、キャリア形成において大きなアドバンテージになるだろう。
もし今、「市場価値を上げたい」と少しでも感じているのなら、このタイミングで一度相談してみてほしい。
あなたの強みをどう伸ばし、どの業界・職種で市場価値を最大化できるのか、プロと一緒に言語化することで、未来の選択肢はぐっと広がるはずである。
以下SaaS業界など成長企業特化型のエージェントのためぜひ活用をしてみてほしい。
キャリアの未来は、今の一歩で大きく変わる。市場価値を“上げ続けるキャリア”を歩むために、ぜひ行動を起こしていただきたい。